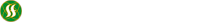- HOME >
- 歴史的大規模土砂災害資料の調査と災害記録伝承の支援
歴史的大規模土砂災害資料の調査と災害記録伝承の支援
我が国では古くから多数の土砂災害が発生してきました。例えば、弘化4年(1847)の善光寺地震や安政五年(1858)の飛越地震等の地震に係わって発生する土砂災害、宝永4年(1707)の富士山や天明3年(1783)の浅間山等の火山に係わって発生する土砂災害、昭和22年(1947)のカスリーン台風や明治43年(1910)の台風と前線等の天候に係わって発生する土砂災害があります。これらの土砂災害は、大規模で局所的に発生する災害や大小さまざまな規模で広域に発生する災害があります。例えば、崩壊土砂が河川に到達することで河道閉塞が生じて天然ダムが形成し、決壊するなどの複合的な災害になります。このような災害では、絵図や古文書、さらには地域での言い伝え、災害関連碑など様々な形の資料として災害記録が伝承されています。また、地域の風習として、寛保2年(1742)の戌の満水が発生した日に家族で慰霊碑やお墓をお参りする等、災害を忘れまいとする文化も残っています。
当機構は、歴史的大規模土砂災害の実態を明らかにするとともに、地域に残る様々な土砂災害資料の調査・整理を行い、土砂災害記録を伝承し地域の防災・減災に資するための災害記録作成を支援しています。また、その災害記録を活用・利用できるように、災害カルテや災害記録地図などのとりまとめも行っています。一方、とりまとめた結果を小学生から大人までが手に取れる情報として、「災害伝承冊子」等を作成するお手伝いをいたします。
土砂災害資料調査と整理
平成23年(2011)の東日本大震災以降、特に歴史災害資料に注目が集まるようになりました。歴史災害資料は、当時の状況を伝え、その時の惨状を伝える貴重な資料です。一方、災害資料は、主に都道府県や市町村、あるいは施設管理者が一次資料や二次資料からとりまとめ、過去の災害実績を公開してきました。近年ではその活用や検証など、実態について改めて検討・検証し、正しい災害の状況を伝承させることが重要視されています。
当機構では、大規模な土砂災害や広域で発生した土砂災害の実態を正しく伝えるために、文献調査、ヒアリング調査、現地調査など、現在に残る様々な情報を基に砂防学、森林科学、地理学などの学際的な土砂災害資料調査を実施しています。また整理に当たっては、災害記録地図として流域全体のどの場所で発生したかとりまとめ、それらの災害実態を一覧にした災害カルテを作成しています。災害と人間は古くからかかわりながら生活してきました。このため、その地に残る文化などもできる限り調査し、反映させて整理します。
 |
 |
| 文献調査結果の説明 |
現地での天然ダム調査 |
土砂災害資料調査と整理
TEL:03-5216-5872 FAX:03-3262-2201 e-mail: